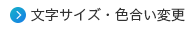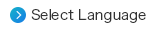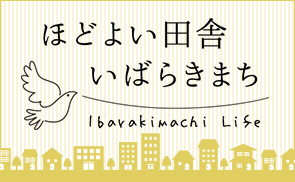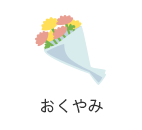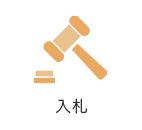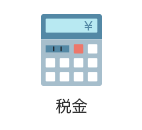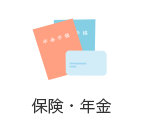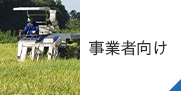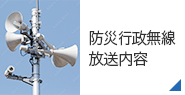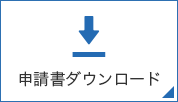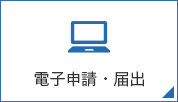国民健康保険税について
国民健康保険税(国保税)とは
国民健康保険税(以下、「国保税」)は、国民健康保険加入者がいる世帯の世帯主に課税される税金です。
納めていただいた国保税は、病気やけがに対する医療費等の給付に使われたり、子どもを出産したときや、死亡したときの給付に使われたりします。
国民健康保険の健全な運営のためにも、日頃から健康を意識し、病気にならないようにしましょう。また病気になっても重症化しないように生活習慣の改善を心がけたり、ジェネリック医薬品を使用したりするなどして、医療費の削減にご協力をお願いします。
国保税を納める人
国保税は、世帯主が納税義務者です。
世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主に対して国保税が課税されます。
国保税の決まりかた
国保税は、国民健康保険の資格を取得した月から発生します。
税額の計算は、「医療分」、「後期高齢者支援金分」、「介護分」について、「所得割」、「均等割」の2つの項目をそれぞれ算出し、最終的に世帯で合算した金額が1年間の国保税となります。
それぞれの項目は、下記の計算で算出します。
- 所得割‥‥課税対象額(前年度の総所得金額から430,000円を控除した額)×所得割税率
- 均等割‥‥被保険者数×一人当たりの均等割額
| 区分 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分※1 |
|---|---|---|---|
| 所得割(税率) | 7.7% | 3.2% | 2.7% |
|
均等割(税額) (一人当たり) |
43,000円 | 18,000円 | 19,000円 |
| 課税限度額※2 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |
※1 介護分は40歳~65歳未満の被保険者がいる場合計算されます。
※2 国保税は1世帯あたりの年間の課税の上限額が定められています。
国保税の納付方法
国保税の納付方法が納付書または口座振替の場合、納期が9期あります。(普通徴収)
今年度の国保税を確定し、期別に分割した金額を課税します。
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
国保税の納付方法が年金から差し引きされている場合は、年金受給月にあわせ6回に分けて納付となります。(特別徴収)
- 4月、6月、8月の国保税(仮徴収)について
国保税は前年の総所得金額をもとに計算しますが、4月、6月、8月については前年の総所得金額が確定しないので、前年度課税額を参考に算定します。 - 10月、12月、2月の国保税(本徴収)について
今年度の国保税が確定し、その額から仮徴収額を差し引いて、3回に分割した金額を課税します。
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仮徴収 | 本徴収 | ||||
【年金差し引き(特別徴収)に該当する要件】 ※以下の項目すべてに該当する方
- 国民健康保険加入者全員の年齢が65歳以上75歳未満であること
- 世帯主の1年間の年金受給額が180,000円以上であること
- 世帯主の介護保険料が年金差し引き(特別徴収)されていること
- 国保税と介護保険料の合計額が年金支給額の2分の1を超えないこと
- 世帯主が国民健康保険加入者であること
【年金差し引き(特別徴収)が止まる要件】※以下のいずれかに該当する方
- 世帯主が年度途中で75歳になる場合
- 65歳未満の方が国民健康保険に加入した場合
- 国保税と介護保険料の合計額が年金支給額の2分の1を超える場合
国保税の軽減について
所得基準による軽減
世帯の所得が一定基準以下の世帯については、国保税の均等割が軽減されます。(世帯主と世帯主以外の国民健康保険加入者の所得で判定をします)
軽減には、2割軽減、5割軽減、7割軽減があります。
軽減判定の基準日は毎年4月1日です。年度途中で世帯が発生した場合は、世帯発生日が基準日となります。
- 2割軽減判定基準額‥基礎控除額(430,000円)+560,000円×被保険者数 (※3)+100,000円×(給与所得者等の数(※4)-1)
- 5割軽減判定基準額‥基礎控除額(430,000円)+305,000円×被保険者数 (※3)+100,000円×(給与所得者等の数(※4)-1)
- 7割軽減判定基準額‥基礎控除額(430,000円)+100,000円×(給与所得者等の数(※4)-1)
※3 被保険者数は、国民健康保険加入者と特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療保険へ加入した方)を合わせた人数です。
※4 一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方
非自発的理由(解雇、倒産など)により離職した場合の軽減
離職時の年齢が65歳未満で、「雇用保険受給資格者証」に記載されている離職理由コードが下記の場合、対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして国保税を計算します。軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。
- 雇用保険の特定受給資格者‥離職理由コードが「11」、「12」、「21」、「22」、「31」、「32」
- 雇用保険の特定理由離職者‥離職理由コードが「23」、「33」、「34」
※雇用保険特例受給資格者証、雇用保険高年齢受給資格者証の方は対象となりません。
※非自発的理由により離職した場合の軽減を受けるためには手続きが必要です。手続き方法については保険課までお問い合わせください。
被用者保険から後期高齢者医療保険へ加入した場合の旧被扶養者への軽減
会社の健康保険などの被用者保険に加入していた方が75歳になると、被扶養者もそれまでの資格を喪失します。これにより国保に加入した65歳以上の方(以下「旧被扶養者」)については、下記の通り国保税を軽減します。
- 所得割…免除
- 均等割…半額(所得基準等で既に軽減されている世帯を除く)
※平成31年度より、均等割への減免適用期間が資格取得日の属する月より2年間となりました。
※旧被扶養者に関する軽減を受けるためには手続きが必要です。手続き方法については保険課までお問い合わせください。
国保税の支払いは口座振替をご利用ください
国保税の支払いを口座振替にすると、「気が付かない間に納期限が過ぎてしまった」「年金差し引き(特別徴収)が止まっていることに気がつかず、督促状が届いてしまった」等の納め忘れを防ぐこともできます。
口座振替を希望の場合は手続きが必要となります。
詳しくは下記をご覧ください。
税務課「町税等口座振替納付制度のご案内」