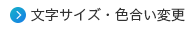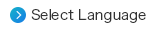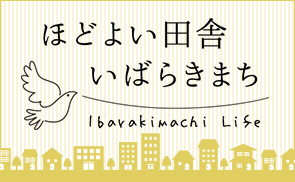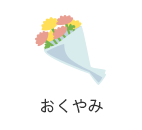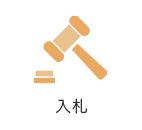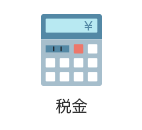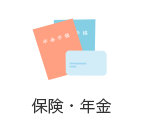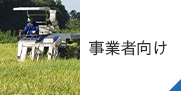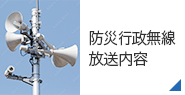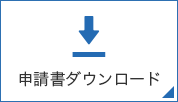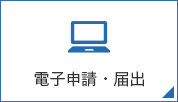町・県民税(個人住民税)について
町・県民税(個人住民税)とは
町・県民税は、一般的に個人住民税と呼ばれ、行政サービスの経費を住民の方に広く分担していただくために納める重要な町の財源です。
町民税と県民税をあわせて町に納めていただきます。
前年1月1日から12月31日までの所得を基に計算し、定額の「均等割」および所得金額に応じて課税となる「所得割」を合計したものが年間の税額となります。納税義務者
- 1月1日に茨城町に住所のある方
- 1月1日に茨城町に住所はないが、茨城町に事業所・家屋敷がある方(均等割のみ課税)
1月2日以降に他の市区町村に転出された場合でも、その年分の町・県民税は茨城町で課税となります。
1月2日以降に納税義務者が亡くなられた場合は、相続人または相続人代表者に納税義務が承継されます。
町・県民税の申告が必要な方
1月1日に茨城町に住所を有し、次のいずれかに該当する場合です。
- 給与所得および公的年金等の雑所得以外の所得がある方(営業所得、農業所得、不動産所得、譲渡所得など)
- 給与所得者で、給与の支払者・勤務先から町に給与支払報告書が提出されていない方
- 医療費控除や寄附金控除を受けようとする方
- 収入がない、または収入が非課税所得(遺族年金等)のみで、どなたにも扶養されていない、または茨城町以外に住所のある方に扶養されている方
※税務署に所得税の確定申告書を提出した方は、町・県民税の申告は必要ありません。
※申告をしないと、証明書が必要な時に取得できない、保険料や保育料、児童手当等の金額が正しく計算されない、医療費の負担が大きくなる場合がある等、様々な不利益が発生します。町・県民税の計算方法
町・県民税は、前年の所得に応じて計算され、均等割と所得割の合計額で計算されます。
- 均等割
一定の所得金額を超えた方に対して、町民税3,000円、県民税2,000円の合計5,000円が課税されます。
- 県民税のうち1,000円は、「森林湖沼環境税」として、森林の保全整備や湖沼などの水質保全に関する事業のためにご負担いただくものです。課税期間は平成20年度から令和8年度までです。
- 森林環境税については森林環境税(国税)について(令和6年度から)をご覧ください。
- 所得割
所得から所得控除の額を差し引いた残りの金額に対して税率をかけて計算します。
- 所得から所得控除の合計額を差し引き、課税所得金額を出します。
- 課税所得金額に税率(町民税6%、県民税4%)をかけます。
- 2で算出した金額から調整控除やその他の税額控除を引き、所得割額を算出します。
町・県民税の非課税範囲
|
所得割と均等割が非課税 |
|
|
均等割が非課税 |
前年の所得が次の金額以下の方
|
|
所得割が非課税 |
前年の所得が次の金額以下の方
|
|
|
扶養なし |
1人扶養 |
2人扶養 |
3人扶養 |
|
令和7年度以前 |
930,000円以下 |
1,378,000円以下 |
1,683,999円以下 |
2,099,999円以下 |
|
令和8年度 |
1,030,000円以下 |
1,478,000円以下 |
1,758,000円以下 |
2,099,999円以下 |
納税の方法
町・県民税の納税方法は、「普通徴収」「給与特別徴収」「年金特別徴収」があります。
- 普通徴収(納付書または口座振替で納付する方法)
- 毎年6月中旬に税務課から納税通知書と納付書を送付します。
- 口座振替を登録されている場合は、納付書は届かず、納期限日に口座から税額が引き落としとなります。
口座振替の申し込みについては【町税等口座振替納付制度のご案内】をご覧ください。
その他の納付方法については、以下をご覧ください。
スマートフォン決済アプリでの納付【スマートフォン決済アプリで町税等の納付ができます】
eL-QR(地方税統一QRコード)を活用した納付【eL-QR(地方税統一QRコード)を活用した町税の納付ができるようになりました】
- 給与特別徴収(給与から天引きで納付する方法)
- 毎年5月中旬に税務課から事業者(勤務先)へ税額決定通知を送付します。
給与特別徴収に関する手続等については【個人住民税(町・県民税)の特別徴収について】をご覧ください。
- 年金特別徴収(公的年金から天引きで納付する方法)
- 65歳以上の方で公的年金等所得に係る税額がある場合、公的年金支給時に町・県民税を天引きします。
- 毎年6月中旬に税務課から納税通知書を送付します。
- 年金特別徴収の対象となる年金の支払額が年額18万円未満の方、年金特別徴収される町・県民税が老齢基礎年金の額を超える方は、普通徴収となります。
年金特別徴収の詳細は【公的年金からの町・県民税(個人住民税)の天引きについて(年金特別徴収)】をご覧ください。
よくあるお問い合わせ
Q1.前年よりも税額が高いようです。
町・県民税は、所得金額と所得控除の内容によって税額を計算します。そのため、前年と比較して収入金額が変わらない、または下がった場合でも、控除内容に変更があった場合は税額が高くなることがあります。
税額が高くなる例として、次のようなことが考えられます。
「前年より給与を多く受け取った」「年金の受け取りを開始した」「扶養控除に変更があった(配偶者や子どもが勤め始めたため扶養から抜けた等)」「確定申告をしていないため適用していない控除がある」「医療費控除の金額が前年より低かった」等Q2.非課税範囲内、配偶者の扶養範囲内で働きたいのですが。
給与収入のみの場合、町・県民税の非課税範囲は収入金額が93万円以下です。収入金額が93万円超103万円以下の場合は、配偶者控除(税法上の扶養)の対象になり、所得税は非課税ですが、住民税が課税となる場合があります。
なお、令和8年度住民税では非課税範囲等が以下の表のとおり変更となります。
また、社会保険の扶養については町・県民税とは要件が異なりますので、配偶者の勤務先にご確認ください。
|
給与収入 |
本人の所得税 |
本人の住民税 |
配偶者が受けられる控除 |
|
103万円以下 |
非課税 |
非課税 |
配偶者控除(扶養) |
|
103万円超 123万円以下 |
非課税 |
課税(※2) |
配偶者控除(扶養) |
|
123万円超 160万円以下 |
非課税 | 課税(※2) |
配偶者特別控除 (扶養ではありません) |
|
160万円超 |
課税(※1) |
課税(※2) |
配偶者特別控除 (扶養ではありません) |
※1 所得控除の額により非課税になる場合があります。
※2 扶養している親族がいる、本人が障害者などで非課税になる場合があります。Q3.茨城町に住んでいないのに、納付書が届きました。
Q4.昨年退職し、現在は働いていないのですが、納付書が届きました。
令和7年度の町・県民税は、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの所得等に基づき計算をします。
納付書が届いた時点では退職している場合でも、令和6年中の所得等に応じて令和7年度に課税されます。Q5.亡くなった家族の分の納付書が届きました。
町・県民税は1月1日にお住まいの市区町村で課税されますので、1月2日以降に亡くなられた方についても、前年中の所得等に基づき税額を計算します。
亡くなられた方の納税義務は相続人が引き継ぐことになりますので、相続される方に納付書を送付します。
納付書を受け取った方が相続人でない場合は、税務課住民税グループにご連絡ください。
Q6.雇用保険の給付を受けていますが、所得として申告が必要ですか?
以下の収入は課税の対象になりませんので、申告の必要はありません。
- 生活保護の給付金
- 雇用保険の給付金(失業手当など)
- 障害年金、遺族年金
- 児童手当等
ただし、次のいずれにも該当する場合は、課税される所得がない旨の町・県民税申告が必要です。
- 1年間の収入が非課税収入のみ、または収入がない
- どなたにも扶養されていない、または茨城町以外に住所のある方に扶養されている